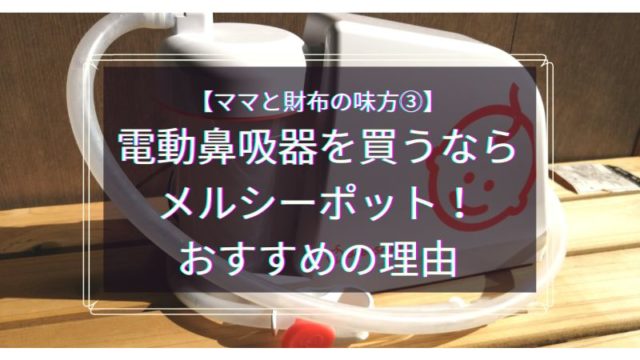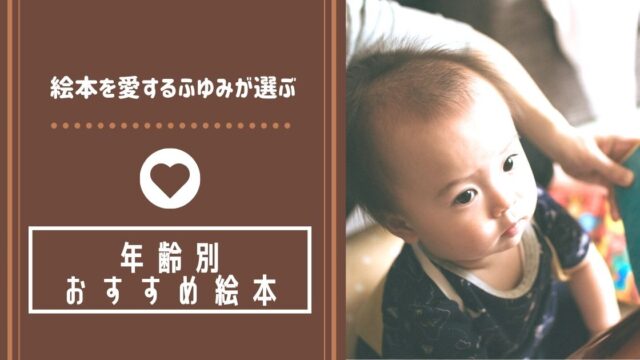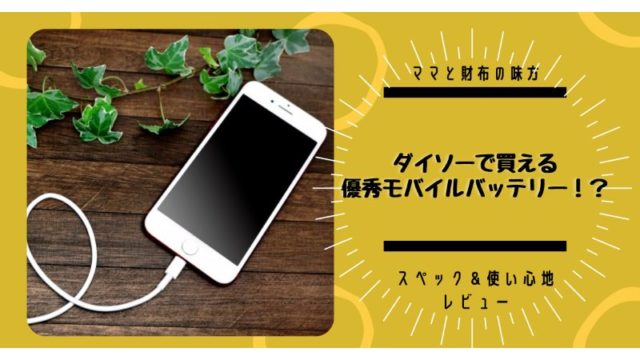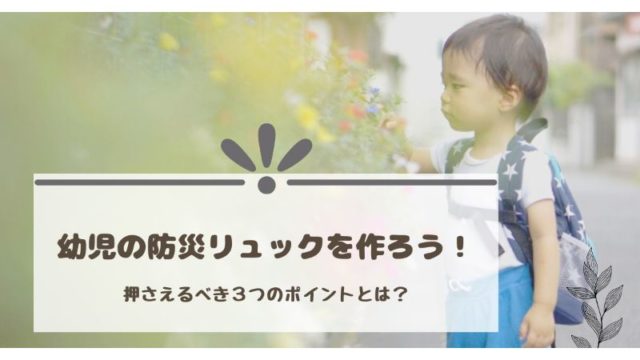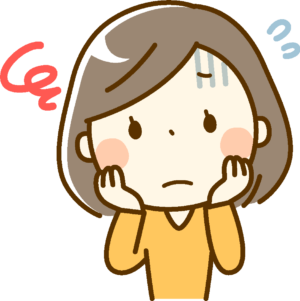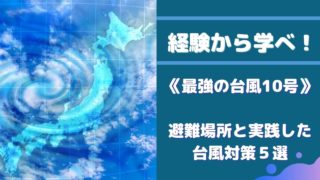連日ニュースで取り上げられる色んな災害状況を知って「次は我が身かもしれない!」と、子どもがいるご家庭では防災に取り組みだしたという方も多いと思います。
そんな中で、中にはこんな悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?
そこで私が試行錯誤した結果、ある3つのポイントに絞って防災リュックを作りました!
ここでは、当時2歳8か月の息子の防災リュック、そして中身について紹介していきます。
※現在3歳半の長男は新しい防災リュックに作り直しました。現在記事作成中です。
- 子ども(年少児)の防災リュックをつくろうと考えている方
- 何を準備したらいいか迷っている方
- そもそも防災リュックが必要なのか迷っている方
そもそも年少児に防災リュックは必要?
基準は『家庭の状況』

ここはご家庭の状況で差が出てきます!
例えば、夫婦と子ども2人、うち1人が乳児で歩けない場合は家族全員がそろっていれば、パパが荷物をもって子どもの手を引き、ママが抱っこ紐で乳児を抱っこする。
こうすれば、走れる子どもに荷物を持たせる必要はないかもしれません。
しかし、もしパパが仕事中で不在だったとしたら?

子どもが2人以上、抱っこできる大人が1人しかいない・・・
という場合は、ママの負担は荷物を背負い、抱っこ紐で乳児を抱き手は子どもの手をひいて避難という事になります。
こうなってくると、ママの負担は相当なものですよね・・・。

また、子どもがいるご家庭の防災リュックはどうしても荷物が増えがちになってしまい、入れたいものが入らない!という事になりかねません。

そんな時、子どもが防災リュックを持つ事で大人のリュックに少しの隙間ができるはずです。その分除外した防災グッズを追加する事ができますよ。
また、防災をちょっとだけ視点を変えてみたらどうでしょう?
子どもの防災リュックを『おでかけリュック』と併用する

そう決意したそこのあなた、そこまで気負わなくてもいいかもしれません!
もし子どもが普段使っているリュックをお持ちであれば、普段入れているもの+α程度でそれなりの防災リュックができますよ。
もしリュック選びでお悩みの方は、こちらの記事も参考にしてください!

リュックの中身選定。私が重視したポイント
1.私の場合「防災リュック=お楽しみ袋、お守り」の存在であってほしい

大人ですら恐ろしい災害。まだ幼い子ども達の恐怖は到底計り知れません。
突如やってきた非日常に、子どもに順応しろというのは無謀ですよね。
そこで私は、防災リュックが子どもにとって“お楽しみ袋”または“お守りや癒し”のような存在になってほしいと考えました。
そして、非日常の中でも日常を感じられる物に重点を置き、以下の2点をメインに荷物を入れていきました。
①おやつ、飲み物

甘い物はリラックス効果があるといわれていますので、大人も子どもも関係なく準備しておきましょう!
子どものおやつの選び方としては食べなれている物、クッキーやビスケットなどの個装袋タイプがおすすめです。
アレルギー持ちの子の場合、避難所で提供される食事が食べられない・・・という可能性も十分にあるので、あらかじめ準備する事でその不安も解消されますね!
個装袋のおやつは種類も豊富なので、何種類か買って残りは備蓄としてストックしておくといいでしょう。
ちなみに飲み物は500mlのペットボトルだと場所をとり重かったので、常温紙パックのお茶やジュース、飲むゼリーなどを入れています。
この手の四角いジュースは、押さえすぎてストローから「ピューッ」とこぼれることもあるので紙パックのドリンクホルダーもセットで入れておくと安心です。
②おもちゃ、絵本類

子どもの気が紛れるように、おもちゃや小さな絵本を入れておきましょう!
お気に入りの物を備えておけば子どもも安心できます。
そんな方に、場所をとらないおすすめのおもちゃをいくつかご紹介します!
手軽に手に入るものばかりなので、追加補充も簡単に出来ますよ♪
【防災リュックにおススメのおもちゃ】

- おりがみ&ペン
- お子様ランチのおまけ
- 小さな絵本
- シール&シール台紙
- 紙風船
どれもかさばらず、軽いのでおすすめです!
折り紙は特に遊び方も無限大ですので、濡れないようにジップロックに入れて保管しておけば雨が降っても心配しなくてすみますね。
ちなみに、以前防災グッズを探していたらこんな商品も見つけました。
ここまで来たら、まさに防災リュック自体が癒しになってくれそうです。
2.子どもが持てる大きさ、重さであるか

災害・避難を想定すると、「これも必要かもしれない」と色んな物を詰め込みがちになってしまいます。
大人であれば多少重くても必要性を理解できるので我慢できます。
でも、子どもだと「持ちたくない!」「いや!」と嫌がられてしまうかもしれません。
その対策として、前述のとおり日頃から同じ中身を入れたリュックを背負わせてお出かけする事をおすすめします!

おやつなど中身が減ってしまった場合はその都度補充していけば、自然とローリングストック法となり、リュックの点検・大きさの見直しをする機会にもつながります!
3.子どもに持たせて使える物か

いくら持っていた方が安心と言っても、子ども自身が物の使い方を理解していなければ意味がありませんよね。
大人が傍にいる前提なので、子どものリュックから取り出して大人が使えば支障はありませんが、なるべく荷物を軽くしたいという場合は荷物選定のポイントになるはずです。
そのため、子どもが使えない物は除外し懐中電灯やホイッスル、手口拭きなどの重要アイテムの使い方を教えておけば、おのずと厳選できるのではないでしょうか。
我が家ではホイッスルの吹き方を練習しました。吹き方だけマスターして、いつ使うかは理解できていませんが「怖いと思った時、助けてほしい時に吹いてね」と繰り返し説明しています。このような小さな積み重ねがいざという時に役立つかもしれません。
リュックの中身はこんな感じ!

以上の3点に重点を置いて、私が完成させたリュックがこちらです!
防災リュックの外装(大きさ、外側の装備品)
このリュックのサイズは縦30㎝×横20㎝×幅10㎝。
当時2歳8か月、身長90㎝、体重13.5㎏の息子には丁度いい大きさでした。



停電してもリュックの場所がわかるように蛍光キーホルダー、そしてホイッスルを外側にセットしています。
そしてこの青くて丸いものは、はずして手に装着すると反射板のリストバンドになります。こちらもダイソー商品。


大人でしっくり、子どもでちょっとゆるいくらいです。ちなみにこのリュックの主、長男えふはこのバンドを
と言って、喜んで装着しています!

防災リュックの中身
防災リュックの中身を全部だしてみました。
食料(主におやつ)

食べ物はおやつメイン。
3食分程度のおやつに加え、飲むゼリーと紙パックジュースを飲料系で入れています。
ただ、なかにはビスケットなど粉砕しやすいお菓子もありますよね・・・。
そんな時におススメなのが、100均にある収納ケースです!

粉砕しやすいお菓子をケースでパッキングすれば、粉砕しないしすっきりまとまるので便利です。ちなみに家にあるタッパーでも代用できます。
ちなみに私がおススメする子どものおやつは、ラムネとビスコです。
ビスコは乳酸菌が含まれているのでお腹に優しいですよね。非常食用として5年間長期保存できる物も販売されています。
ラムネはブドウ糖でできているのですぐにエネルギーに変換できます。大人の非常食として警視庁の災害対策課からも情報発信されていました。
おもちゃ、図鑑など
そして子どもにはかかせないおもちゃ類。


(撮影の際にミニカーは持ち去られました。)我が家ではお気に入りのミニカーや、100均で購入した飛行機のおもちゃ、折り紙等を入れています。中でも特におすすめしたいのがマックのハッピーセット図鑑。
マックのハッピーセットでは、おもちゃか絵本・図鑑を選ぶことができます!
この図鑑シリーズは、その小学館の図鑑NEOシリーズのミニサイズ版です。本屋さんの学童コーナーで見かけるのではないでしょうか?
ミニチュア版だからと言ってあなどってはいけません・・・。
図鑑の内容も充実しており、シールやブーメランなどのおまけがついていることも!薄くてかさばらないのも大きな魅力です。
また災害時だけでなく、結婚式に出席する際や遠出した時の時間つぶしとしても有効です!
これらを濡れないようにジップロックに保管しています。

その他
その他にはこのような物を入れています。(ジップロック保管)

- オムツセット(紙パンツBIG2枚、残り少ないおしり拭き、BOSゴミ袋数枚)
- ウエットティッシュ
- 使い捨てカイロ1枚
- 着替え1セット
- 折りたたみできるコップ
- レジャークッション


コップはセリアの商品で90ml入ります。外出するときは水筒をいつも持参するので、お茶をこのコップに入れて飲ませています。


レジャークッションもセリアの商品です。大人1人座れる位の大きさはあります。公園でおやつを食べる時にはこのクッションに座らせています。
ズボンの汚れを防ぐ他、底冷えの対策にもなりますよ!
※現在3歳半になった長男は、新たにリュックをつくりかえました。年齢に合わせてリュックの見直しもしていきましょう!現在記事作成中です。
最後に~子どもに安心を与えられるのは貴方です!

こうしてみると、防災だ!と気負わずとも楽しく防災リュックを作る事ができるのではないでしょうか?
大切な我が子の笑顔を守れるのは私たち大人、そして親です。
子ども達に怖い思いをさせないために、そして大切な笑顔を守るために楽しく防災リュックを作ってみませんか?
最後までお読み頂きありがとうございました!